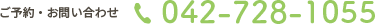症状がなくても糖尿病なの?
糖尿病と診断されるきっかけはひとそれぞれです。のどが渇いたり、疲れやすいなどの自覚症状から医療機関を受診して、糖尿病と診断される場合や、何の自覚症状もなくても検診や人間ドックで、糖尿病と診断される場合もあります。
糖尿病と診断されるには基準値となる数値があり、必ずしも症状があるとは限りません。
糖尿病の患者さんの多くは尿に糖が出ます。これを「尿糖」と呼びますが、糖尿病は「血糖値が高い状態が続く病気」であり「尿に糖が出る病気」ではありません。尿糖は糖尿病の発見につながる手がかりとなり、腎臓の機能が正常であれば、血糖値がある濃度(閾値)を超えると尿糖がでてきます。閾値となる血糖値は160~180mg/dlですが、高齢者では閾値が高くなるなど個人差もあり、逆に血糖値が高くても尿糖が出ないひともいます。
そのため糖尿病の診断には尿糖は用いられず、血糖値と慢性高血糖の指標であるHbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)が用いられます。
血糖値とHBA1Cで確定診断を
糖尿病と食事

糖尿病とは慢性的な高血糖を特徴とする病気です。 確実に診断するには血液検査で血糖値がどのくらいか調べます。 血糖値は食事や運動などにより変動しますが、健康なひとでは朝食前の血糖値がもっとも低く71~109mg/dlの範囲となります。 食事をとると血糖値は上昇し、食後60~90分でもっとも高くなりますが、正常であれば食後2時間後の血糖値が140mg/dlを超えることはありません。
朝食前の血糖値が126mg/dl以上、あるいは食後の血糖値や、 ブドウ糖の負荷試験を行って2時間後の血糖値が200mg/dl以上であれば糖尿病が強く疑われ「糖尿病型」と判定されます。